イノベーションはどうしたら起こせるの!?
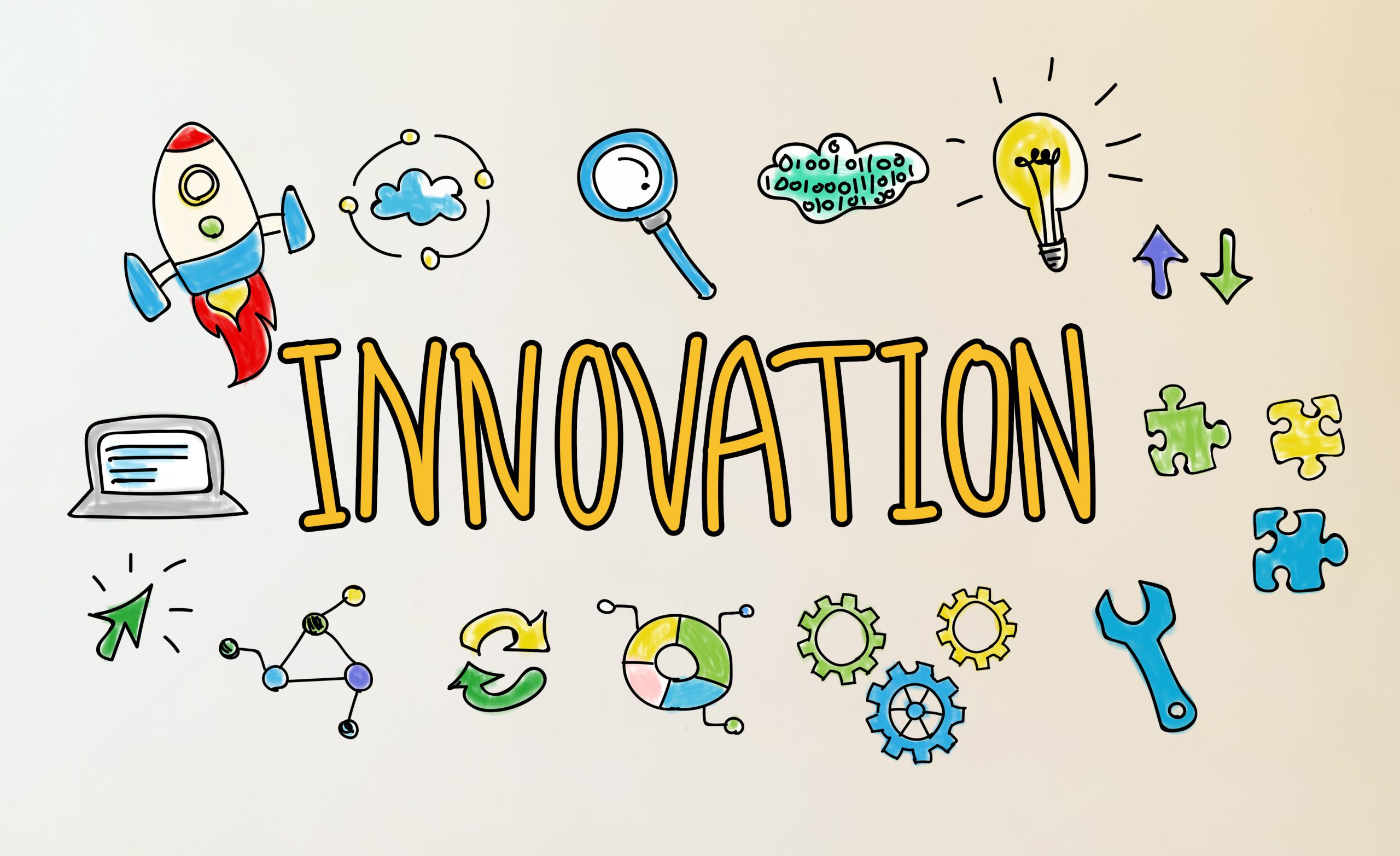
私の研究テーマはこんな感じです
「どのようにしたらイノベーションが起こせるのか?」に関心を持っています。イノベーションは、技術革新とも訳されますが・・・もっと対象とする範囲が実は広いものです。段違いに世界を進化させるモノやサービス、手段といえるでしょう。組織が大きくなり、人数が増えてくると、イノベーションを起こせなくなる理由がたくさん生まれてきます。その理由と解決方法を研究しています。イノベーションが日本や世界中からあふれだす、未来を見てみたいのです。
こんなこと知りたい、話し合いたい、教えてほしい!
職場や学校、地域でイノベーションが起こしにくいと思った理由を教えてほしいです。さらに、イノベーションを起こしやすくするために共に取り組んでくれる仲間も歓迎します。
これが私の得意技です! このことなら私に聞いて~
経営学が専門であり、経営コンサルタントもしてきたので、組織イノベーションやマーケティング、マネジメントに関する知識を持っています。
“イノベーションはどうしたら起こせるの!?” に対して22件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。

科学系の人間で少し狭いお話になってしまうかもしれませんが,最初から何か目的を持って「何かを作り出そう」として考えてやるだけでなく,結構「失敗したからそれをなんとかしたい。」など,なんらかのトラブルシューティングをしている時にアイデアが浮かび,これは(別の)イノベーションにつながるのでは?と思うことがあります。でも,失敗が許されにくい世の中になってきたなあ。。。と感じます。
コメントをいただきありがとうございます。失敗などのトラブルシューティング時におけるアイデアの着想について、大変重要な視点だと思います。世界のホンダの創業者、本田宗一郎は、困ることの大切さについて「いろいろな問題にぶつかって困ることは、チャンス」と述べています。イノベーションを起こすには、失敗が許容されるそのような職場環境をつくり、誰しもが試行錯誤を行える環境の整備も必要となるでしょう。
前例踏襲、若手はだまっていろ、こういう組織はイノベーション生まれませんよね!
前例踏襲に関するコメントをいただきありがとうございます。確かに人には、現状維持バイアスが起こり、これまで行ってきたことや従前の仕組みや制度がよいものであると思い込みやすい傾向があります。このバイアスは、リチャード・ゼックハウザーとウィリアム・サミュエルソンらの研究により明らかになっています。現状維持バイアスがあることを認識するとともに、現状維持を続ける危険性を明確にし、若い人たちの意見も取り入れながら、新たな変化を試験的に起こしていくことが必要かもしれませんね。
様々な分野の人との交流が重要と思います。
コメントをいただきありがとうございます。おっしゃる通り、イノベーションを起こすには、さまざまな分野の人との交流が大変重要となります。古くは、イギリス、オランダ、スペイン、メキシコ、中国など、自由な交易により世界中のアイデアが出会い、変化し、イノベーションを起こしてきました。実は、人口統計学の視点では、圧倒的に人口が多い都市部で起こりやすい現象なのです。ただ、人口が少ない中山間地域では起こしにくいかと言われれば、そのようなこともありません。中山間地域でイノベーションを起こすには、多様性のある人たちが集い、脳と脳が交流し交わる機会を意図的に増やしていくことが重要となることでしょう。
イノベーションが起きない理由は、人間が他人任せになっているからだと思います。(口だけになっている)行動を起こす前に、口で言うだけ言ってスッキリする。これで人間の心は満たされてしまうのだと思います。だから行動を起こさないで、誰かにまかせて賛同するだけになると思います。
行動を起こす前に口頭で心が満たされてしまうとのコメントありがとうございます。そこで満足してしまう人が確かにいることでしょう。人は、問題に対峙したときに、4つの行動レイヤーに分けることができます。①問題に気づかず無関心、②問題に気づくが口を出さない人、③問題に気づき口を出す人、④問題に気付き、口を出し行動に移す人。ご指摘のタイプは③番となり、批評家ともいえ、批判ばかりするだけで何も問題解決には貢献できていない状態です。さらに、批判的な発言により当事者を傷つけてしまうことすらあります。やはり、他人任せにせず、問題に寄り添い、建設的な意見を出し合い、共に協力して主体的な行動に移す人材が求められている気がします。
利益をまず考えないと会社としてはいけないためなかなか新しいことができない。
コメントをいただきありがとうございます。ご指摘の通り利益優先では、新自由主義の中で、競争や経済効率を優先した社会を構築してきたことによる弊害も生まれています。利益ファーストでは、確かに社会をよくする活動に限界もありそうです。最近では、ゼブラ企業などの企業利益と社会貢献という、相反する理念の両立を目指した企業も生まれています。社内で新しいことができない場合には、会社の組織の中に、実験的な取り組みを行う出島をつくり、予算を社長直轄などにおいて、長期的な視点で取り組みをはじめてみることもよいかもしれません。
ゼロからイチを生み出すのは難しくても、既存の技術や考え方に何かを足す、引く、合わせるだけで、新たなイノベーションは生まれる。意外と身近にある!!
既存の技術や考え方を足す、引く、合わせるだけで新たなイノベーションが生まれ、意外と身近にあるとのコメント、誠にありがとうございます。私も同感です!『トム・ソーヤーの冒険』で知られる作家であるマーク・トウェイン氏は、「新しいアイデアなどない。古いアイデアを集めて頭のなかで万華鏡のようなものに放り込むだけ」と述べています。万華鏡を回せば新しい景色が見えて、それらの組み合わせは、無限大。しかも材料は、新しいものなどなく、見慣れた材料ばかりなのです。ぜひ、身近なものを組み合わせて、イノベーションを起こしたいですね。
イノベーション、新たなアイデアは既存体制にしがみつく人たちに拒まれる印象があります…。やってやろーぜティーンエージャー!
コメントありがとうございます。権威主義や前例等主義などの既存体制下では、自由を源泉とするイノベーションは阻害され、拒まれて起こしにくくなります。実は、組織で新たなアイデアを生み出すには、自由に思ったことを発言できる心理的安全性が何よりも大切なことが、グーグルのチームの効果に影響を与える因子を特定する研究「プロジェクト・アリストテレス」で明らかになっています。アイデアが若者から生まれやすい組織をつくっていく必要がありそうです。私も学生や社会人の若い人たちに期待しています!
改革を好む人と継続を好む人と様々な人がいます。どの人もおいていかない「イノベーション」ならべすとですね。ex.交通系ICカードのようなもの
コメントにありました、改革を好む人と継続を好む人と様々な人がいる現状を踏まえて、どの人においてもイノベーションが起こせる社会が確かにベストですね。私もイノベーションを特別から標準にする活動を通じて、日本や世界からイノベーションがたくさん生まれる、そのような社会を見てみたいです・・・学生とともに。
イノベーション、出る杭は打たれる…これでは何も生み出すことはできないと思います。皆が意見を出し合える環境になってほしいものです。これからの若い人に期待大!
コメントをいただきありがとうございました。確かに現代では、イノベーティブな取り組みを試みようとするとき、「出る杭は打たれる」現象が起こり、よいことでも実現せずに終わってしまうことが発生しています。そのようなことが起こればやる気を失い、もう2度と取り組まないと考える人も出てくることでしょう。若者の挑戦の芽を上司や管理職が詰んではなりませんね。私は、新しいことをはじめるときに、8割が反対するくらいでちょうどよいと思うようにしています。おそらく、1〜2割の人しか理解できていないものが新しいことともいえるでしょう。もしも、8割が賛成する内容でしたら、ほかでも多く実施されていて古くなっている証ともいえるからです。これから、新たなものを導入しようとしたときに、もし反対されたら新しいからだ自分に言い聞かせることもやる気を失わないための方法の1つかもしれません。若い人たちのアイデアにも期待しましょう。
今の若い子たちが自ら考えたことを発信したりやりたいことにためらいなくチャレンジできる世の中になってほしい
やりたいことにためらいなくチャレンジできる世の中になってほしいとのコメントありがとうございます。私もお考えに賛同させてください。PGF(プルデンシャル・ジブラルタ・ファイナンシャル)生命が実施した、2021年の還暦人に関する調査で「自身の今までの60年をあらわす漢字(1字)」を明らかにしています。結果は、男性1位:「忍」、女性1位:「楽」の結果でした。この結果から男性の「忍」には辛抱や忍耐の人生であったこと、女性の「楽」には楽しいことがあった人生であったことを示しています。どうか、若い世代が人生を振り返ったときに、辛抱や忍耐の人生ではなく、やりたいことにチャレンジする挑戦の「挑」が増えることを願っています。
イノベーションが起きにくいというより、それが「イノベーション」と認知されていないのも理由としてあげられるのかと思いました。やはり「技術革新」という訳からテクノロジー的側面をイメージしてしまいますが、教育現場に限っても「イノベーティブな」取り組みはたくさんあるかと思いました。
コメントをいただきありがとうございます。確かに、イノベーションを少し長いスパンで捉えると段違いの進化に見えるものの、短いスパンでみると変化が少しずつ生まれていて、どこからイノベーションなのか気付けないことが現実には起こっています。おっしゃる通り、イノベーションは、日本語訳「技術革新」として、大変狭い範囲の意味でとらわれることがあります。実は、総務や会計、営業、そして教育にもイノベーションを起こすことができます。ぜひ、社会の中でイノベーティブな取り組みを増やしていきたいものです。